PCラック(ホワイト)
2台目のPCラックを作ります。
端材から必要な長さ分の板を作るため、板矧ぎしました。
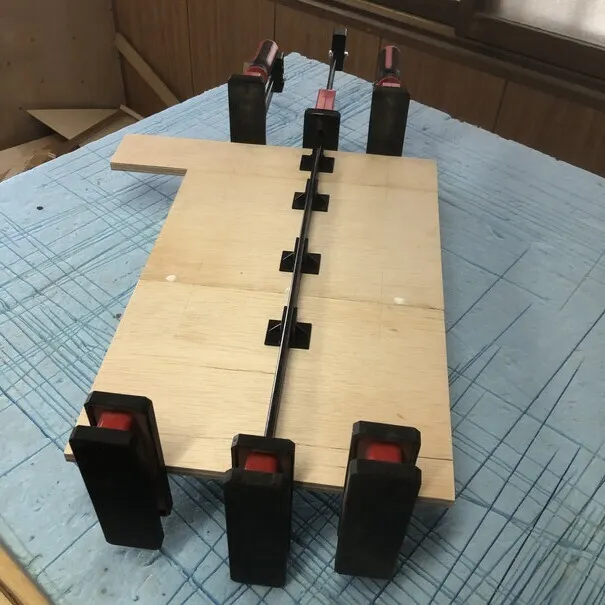
今回はホワイトを使用します。
木目は見えなくなるので、木のつなぎ目も分からなくなるはず……。

サンディングシーラーを塗っておきます。
別に塗らなくてもいいのですが、どのような変化があるのか、3年くらい観察する予定です。
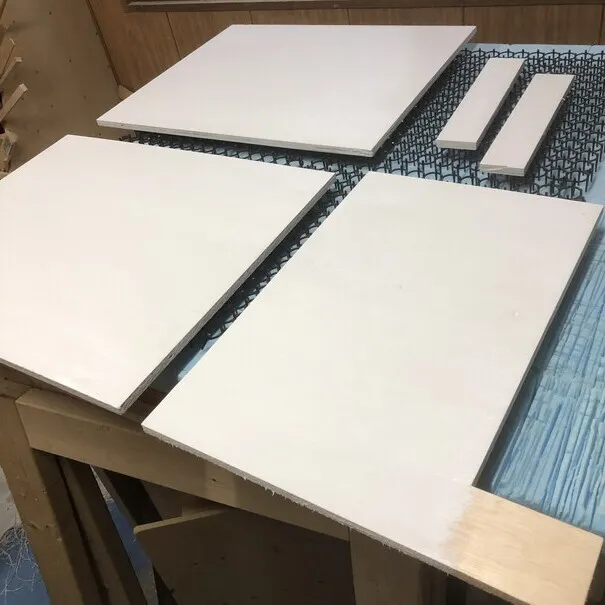

ネコ避けは、先が尖っているので跡が残る場合があります。そこで、ペットボトルのキャップをばらまいて、上に板を乗せました。
乾いてから、ビスケットを使って仮接合します。

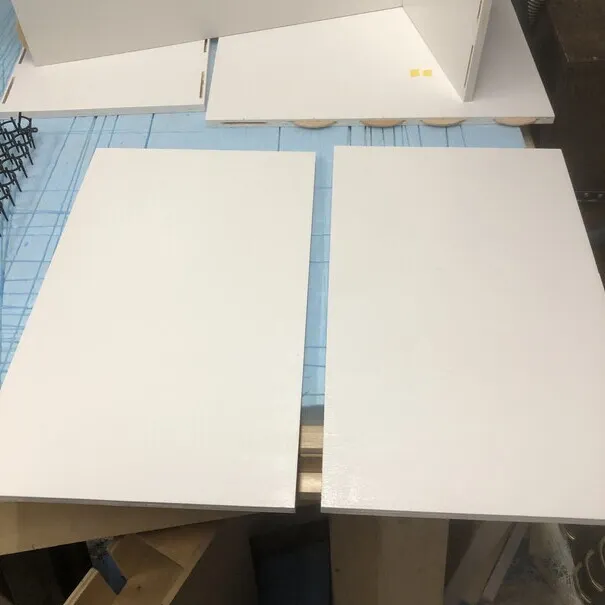
箱のかたちには組めそうです。
問題は棚板をうまく接合できるか。ここが今回の山場です。
!(`・ω・´)
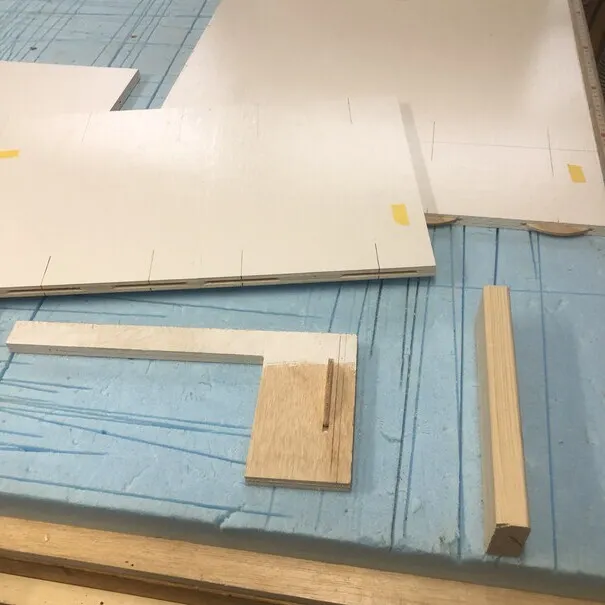
切り落とした合板の使わない部分でテストしました。
ジョイントカッターの底から刃まで10ミリの高さがあります。厚さ20ミリの木材なら、そのまま使えばど真ん中を彫ることができますが、使用する材は11ミリ。ズラして使う必要があります。ストッパーの位置をもっと下げる必要があります。どのくらい下げればいいか計算します。
φ(・д・。)

色見本をストッパー代わりに使って、板のど真ん中にビスケットの入る穴を彫っていきました。
うまく入るかな……?

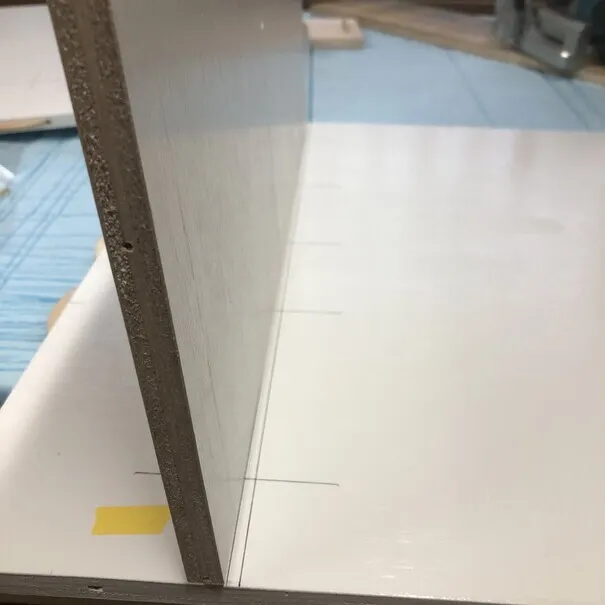
どうやら成功したみたいです。
( ゚д゚)ォォ…
では、ボンドを使って接合していきましょう。

と、ここまで来て、組み立てに順序があることに気づきました。
ネジ留めで作ることが多いので、外箱から作って棚板は後で入れていました。これ、内側→外側の順に組まないといかんのでは……?
( ゚д゚)ハッ!
ダボ接合やビスケット接合のように、出っ張りがあると、後から棚板を入れることはできませんからね。ボンドが乾く前になんとかしないと。急げ急げ~。
(@д@_)

底が上になっていますが、なんとか組み上がりました。
それにしても作業場の湿気のせいか、ビスケットが膨張して1/3が溝に入りませんでした。そこで和菓子の中にシリカゲルの親戚みたいなものがあったので、入れておくことにしました。「乾燥剤」と書いてあったので、ないよりあったほうがいいでしょう。


では、引き出しをふたつ作成していきます。
端材からパーツを切り出しました。
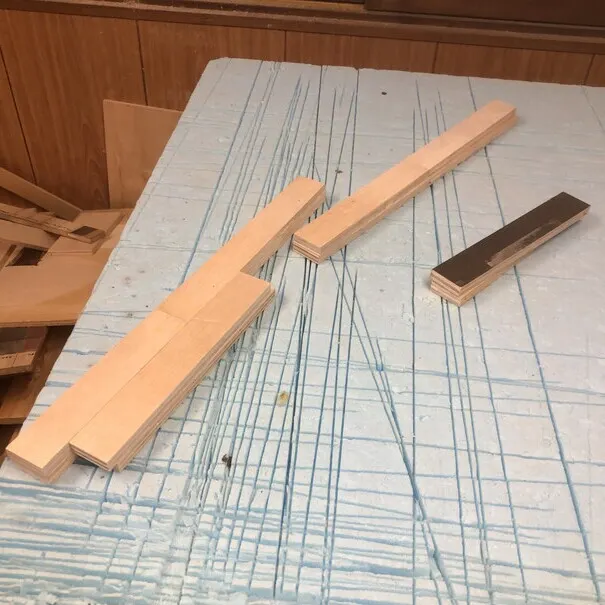
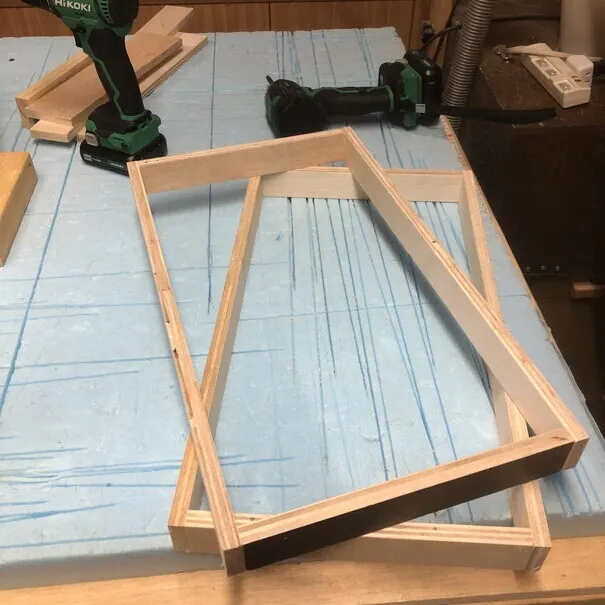
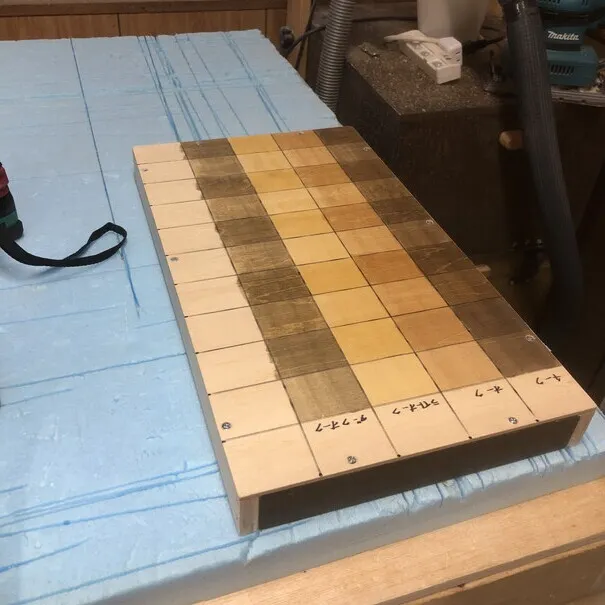
引き出しの底板には、色見本として作ったシナ合板を使いました。
さて、締め付けていたクランプを外して本体をよく観察したのですが、なんだか直角が出ていないような気がします。
ウーン (Θ_Θ;)


スコヤで確認すると、隙間ができていますね。つまり、直角じゃないということ。
引き出しを乗せる擦り桟も接合したのですが、ここまで来て問題が出るとは……。
( ゚д゚)ガーン!
……。
……。
気にしない~♪
(≧▽≦)
というわけで、引き出しを入れて前板を付けました。
ストッパー付きのキャスターは前輪のみ、計4つ取り付けてあります。
今回は丁番で扉を付けます。

ここへ来て、直角でないことの影響が出てきました。扉は長方形として作っていますが、引き出しとの間隔が一定にならないんですね。左のほうが2ミリ余計に空いてしまいます。そこで、扉の上の部分だけ三角状に切り落としました。
これで外見上は引き出し、扉が等間隔に接合されているように見えます。が、扉の開閉時にキィキィ音を立てるようになりました。こんなところで影響するのか~。
ウーン (Θ_Θ;)
ともかく、切り落とした部分だけ再塗装して、ニスを塗布しました。
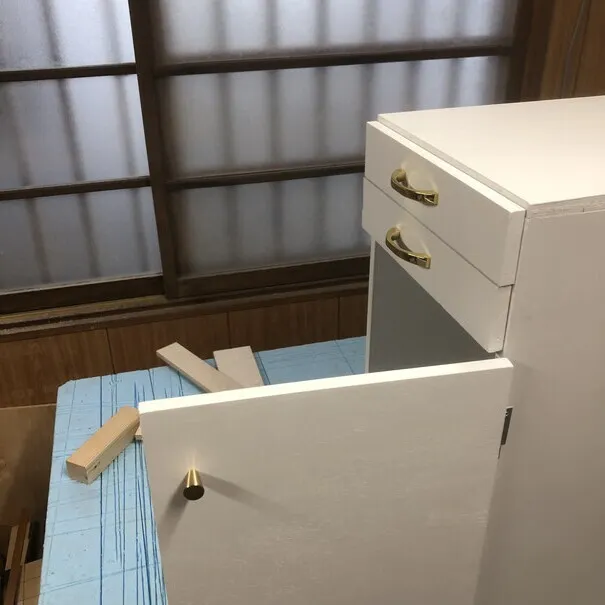
完成! パソコンを収納してみます。
って、ほとんど見えないやん。


上側のスペースを狭くして、その分、引き出しの高さを増やせないかなーと思っていましたが、狭くしなくてよかったです。USBを真上から差し込む筐体なので、上側にある程度のスペースが必要なんですね。設計変更しなくてよかったー。
\(^▽^)/
引き出しの底板は、色見本を作る予定だったシナ合板なので、格子状に線が入ったままです。何か収納すれば気にならなくなるでしょう。リメイクシートを貼ってもいいかな。


今回、引き出しを支える擦り桟は、金属製ではなく、Lジョイナーという1.82メートルが100円以下のものを使っています。やわらかいです。果たして使用に耐えうるか? サンディングシーラーを塗ったのも試験的意味合いがあります。まー、結果が分かるのはしばらく先ですねー。





ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示2台目完成おめでとうございます👏
とても参考&勉強になりました✨